2015年3月7日(土)
庭をつくる人・1
エゾリスの悩みを聞いてあげる心優しき男。
アカイケ ヒロオミ。
「優れているという事は、優しいという事なんだよ。」

「ルールルルルル...............」
フジヤマ ユウヤ。

つれづれ草に水は浅いほどよいと書いてある。わたくしは子供のころは大概うしろの川の磧で暮した。河原の中にも流れとは別な清水が湧いていて、そこを掘り捌さいて小さいながれをわたくしは毎日作って遊んだものである。ながれは幅二尺くらい長さ三間くらいの、砂利をこまかに敷き込み二た側へ石垣のまねをつくり、それを流れへ引くのであったが、上手かみての清水はゆたかに湧きながれて、朝日は浅いながれの小砂利の上を嬉々と戯れて走っているようであった。自分はところどころに小さい橋をつくり、石垣には家を建て、草を植え花を配したものであった。此の頃になってつれづれ草ばかりでなく、水は浅く川はば一ぱいにながれて居る方がよいと思った。
水というものは生きているもので、どういう庭でも水のないところは息ぐるしい。庭にはすくなくとも一ところに水がほしい。つくばい(手洗鉢)の水だけでもよいのである。乾いた庭へ這入ると息づまりがしてならぬ。わたくしたちが庭にそこばくの水を眺めることは、お茶を飲むと一しょの気持である。
わたくしは蹲跼つくばい(石手洗い)というものを愛している。形のよい自然石に蜜柑型の底ひろがりの月がたの穴をうがった、茶人の愛する手洗石である。庭のすみに置くか、中潜りの枯木戸の近くに在るものだが、此のつくばいの位置は難むずかしくも言われ、事実、まったくその位置次第で庭相が表われやすい。わたくしは茶人や庭作人の眼光外にいるものだが、しかしこの位置だけは定石であるだけに踏みやぶるわけにはゆかない、つくばいだけは背後うしろの見透しが肝心である。矢竹十四五本ばかりうしろに見せ、前石(つくばいに跼んで手を洗う踏石)の右に矮ひくい熊笹を植えるのもよい、とくさは手洗いにつきすぎて陳腐であるから、若しこれを愛する人があるならば此のつくばいから四五尺隔はなれたところに突然に植えて置く方が却ってよかろう。しかしつくばいとのつなぎのために砥草とくさのわきに棄石がなければならぬ。或る庭で見たのであるが唯の一本の枝ぶりのよい山茶花の下につくばいがあり、水さばきの鉢前の穴の上に山茶花四五弁こぼれている風情は全くのよい姿をしていた。これは偶然に初冬のころだったので目を惹いたのであろう。
いっそ此のつくばいのうしろに猗々たる藪畳があっても、つくばいが相応に立派なものだったら百畳の竹をうしろに控えていても、しっかりと抑えて据えられるであろうと思う。主としてつくばいは朝日のかげを早くに映すような位置で、決して午後や夕日を受けない方を調法とする。水は朝一度汲みかえ、すれすれに一杯に入れ、石全体を濡らすことは勿論である。その上、青く苔が訪れていなければならぬが、一塵を浮べず清くして置かなければならぬ。口嗽ぎ手を浄めるからである。
兼六公園にある成巽閣の後藤雄次郎作の四方仏は、小流れに沿うて据えられ、石仏四体が刻まれている。小流れの両側に奇石珍木を配してあることは言うまでもない。平常閉してある庭中の幽雅は木々草石の上にこもっていて、穏かなすれない極寂ごくさびがあった。上流に突然とした砥草の茂りがあるのも、老巧な植木やの手なみが窺われていた。わたくしはこの手洗いに仏を刻んである因縁を窃ひそかに考えて見て、清きが故なお浄かろうとする意図を床しく思うた。茶庭では燈籠は木のうしろにいても、手洗いは上手かみてに立たなければならなかった。つくばいは人の手にふれるものだけに、たとえ隅の方にあっても品格は上手に位するものである。瑞雲院の庭のつくばいは二方の踏石から辿ることになり、一枚の短冊石を踏んで行くのであるがその打ち方も厳格であった。兼六園の池のきわの手洗いは大石であるが、三抱えくらいの椎の大樹の根元にしっかりと置かれ、雄心を遣るに豪邁であった。わたくしはまだこれほどの大樹の根元に置かれた手洗いを見たことはない。
つくばいの品格は最も秀すぐれたものでなければならず、形は大きくも小さくもない、程よい見馴染みなじみの快いものでなければならぬ。何となく奇岩めいた姿つきで、高峯一端の清韻を帯び、そのうえ雲霧を掻き起こすような気もちのものを尊ぶことは実際である。聊斎志異の白雲石の口碑のように穴あり時に綿のような雲を吐かねばたらぬ。そして鉢(水を入れるところ。)の中は古鏡のように澄み古色自ら在る体のものでなければならない。蒼い底に水をたたえた一基のつくばいは、何か庭の中に人あって鏡を見ているような心もちを起させるようである。実際、一掬の清水はよく庭裏の誠をうつすからである。
手洗いにはわたくしの知っている限りでは、普通のつくばいの外に、しゃれた石臼のような伽藍形があり、それは円い石に円い水鉢がうがたれている。最もっとしゃれたのに唐船というのは、自然石の鍬のような反りを持った石の左よりに水鉢があって、むかしの唐船のへんぽんたるに似ていて風致あるものである。司馬温公われまつばというのは三方に峯のある石のまん中が水鉢になり居り、風雅であるが居処いどころをきらうものであるから、鳥渡ちょっと据えるところに難しいしろものである。円星宿は普通の胴円どうまる通しの手洗いであるが、石水壺は先でひろがり底すぼまりの置水鉢で、石材次第で栄えるものだが、わたくしは嫌いである。却って石水瓶の三方取手のある枕型の胴すぼまりを面白いと思っている。支那朝鮮によくある大壺取手づきに似ていて、石であるため陶器以上のおもしろさである。陶器と石とは孰どちらが面白いかと言えば、味の細かいことは到底陶器には及ばないが、一味通じた底寂しい風韻枯寂の気がながれ合い、ときに陶器に見味うことのできぬところに、わたくしの心を惹き何かを思うさま捜らしてくれるのである。そのほか方星宿の四角なのもあるが、取り立てて言うまでもない。富士形、ひょうたん形に至っては、われわれ雅人と称するともがらには要なき俗手洗いである。つくばいは飽迄自然石を穿ったもので水鉢の磨きも叮嚀に寂然たるものでなければ面白くない。赤日石林気というのも又つくばいの銘でなければならない。
筧手洗いというのは高みにある手洗鉢に筧の水をしたたらすのであるが、これは生きているようで風致湧くごときものがある。凡兆の「古寺の簀の子も青し冬がまへ」という句があるが、何となくこの句の趣のような山住み山家の気持を表わすもので、春おそい日の永いころに筧の滴る音を書屋で聴くのはこころ憎いものである。その滴る水の流れ口を次第に低めにして自然に敷砂利しきじゃりの間を縫うてゆく趣の深さは、わざと細流をしつらえるより幽寂新鮮味は数倍するであろう。
四方仏というのは角胴四面に仏をきざんだのであるが、清韻愛すべきものである。わたくしは所謂難波寺形という大樹の下に据える手洗いに、姫蔦の蔓を這わしたことがあったが、蔦が石面一杯に蒸しつき、葉と葉との間に一掬の水が閑のどかに澄んでいるのは、まことに天来の穏かさを保って、限りなく美しいものである。茶庭では手洗いの前に湯桶手燭を置き、茶席の会中立前の所作の一つになっているそうである。わたくしは茶の方は詳しくないが、其行きとどいた精神にはいつも敬服している。茶道はまた色道に通ずというわたくしの哲学は、古今の茶道大義でなければならぬと思うている。清浄の中にいて色道を思うの情は、林泉に踞して亦垂鉤の境に蹲むと一般であろう。水光日を浮べ出て転た佳人を想うの心を誰も咎めるものはいない。こんな色道は枯れ侘びてなお余燈に対むかうようで、わたくしは好きである。遠州好みの茶庭のように大樹一本、小樹四五本、踏石を分けた中庭括り、八ツ窓茶室というような感じである。そのように整うところに何かの色があった。さびももとを掘じくり出すと何かの色が出て、褪めていて懐しいものである。
「庭を造る人」改造社
つくばい
1927(昭和2)年
.
アカイケ ヒロオミ。
「優れているという事は、優しいという事なんだよ。」

「ルールルルルル...............」
フジヤマ ユウヤ。

「庭をつくる人」
室生犀星
つくばいつれづれ草に水は浅いほどよいと書いてある。わたくしは子供のころは大概うしろの川の磧で暮した。河原の中にも流れとは別な清水が湧いていて、そこを掘り捌さいて小さいながれをわたくしは毎日作って遊んだものである。ながれは幅二尺くらい長さ三間くらいの、砂利をこまかに敷き込み二た側へ石垣のまねをつくり、それを流れへ引くのであったが、上手かみての清水はゆたかに湧きながれて、朝日は浅いながれの小砂利の上を嬉々と戯れて走っているようであった。自分はところどころに小さい橋をつくり、石垣には家を建て、草を植え花を配したものであった。此の頃になってつれづれ草ばかりでなく、水は浅く川はば一ぱいにながれて居る方がよいと思った。
水というものは生きているもので、どういう庭でも水のないところは息ぐるしい。庭にはすくなくとも一ところに水がほしい。つくばい(手洗鉢)の水だけでもよいのである。乾いた庭へ這入ると息づまりがしてならぬ。わたくしたちが庭にそこばくの水を眺めることは、お茶を飲むと一しょの気持である。
わたくしは蹲跼つくばい(石手洗い)というものを愛している。形のよい自然石に蜜柑型の底ひろがりの月がたの穴をうがった、茶人の愛する手洗石である。庭のすみに置くか、中潜りの枯木戸の近くに在るものだが、此のつくばいの位置は難むずかしくも言われ、事実、まったくその位置次第で庭相が表われやすい。わたくしは茶人や庭作人の眼光外にいるものだが、しかしこの位置だけは定石であるだけに踏みやぶるわけにはゆかない、つくばいだけは背後うしろの見透しが肝心である。矢竹十四五本ばかりうしろに見せ、前石(つくばいに跼んで手を洗う踏石)の右に矮ひくい熊笹を植えるのもよい、とくさは手洗いにつきすぎて陳腐であるから、若しこれを愛する人があるならば此のつくばいから四五尺隔はなれたところに突然に植えて置く方が却ってよかろう。しかしつくばいとのつなぎのために砥草とくさのわきに棄石がなければならぬ。或る庭で見たのであるが唯の一本の枝ぶりのよい山茶花の下につくばいがあり、水さばきの鉢前の穴の上に山茶花四五弁こぼれている風情は全くのよい姿をしていた。これは偶然に初冬のころだったので目を惹いたのであろう。
いっそ此のつくばいのうしろに猗々たる藪畳があっても、つくばいが相応に立派なものだったら百畳の竹をうしろに控えていても、しっかりと抑えて据えられるであろうと思う。主としてつくばいは朝日のかげを早くに映すような位置で、決して午後や夕日を受けない方を調法とする。水は朝一度汲みかえ、すれすれに一杯に入れ、石全体を濡らすことは勿論である。その上、青く苔が訪れていなければならぬが、一塵を浮べず清くして置かなければならぬ。口嗽ぎ手を浄めるからである。
兼六公園にある成巽閣の後藤雄次郎作の四方仏は、小流れに沿うて据えられ、石仏四体が刻まれている。小流れの両側に奇石珍木を配してあることは言うまでもない。平常閉してある庭中の幽雅は木々草石の上にこもっていて、穏かなすれない極寂ごくさびがあった。上流に突然とした砥草の茂りがあるのも、老巧な植木やの手なみが窺われていた。わたくしはこの手洗いに仏を刻んである因縁を窃ひそかに考えて見て、清きが故なお浄かろうとする意図を床しく思うた。茶庭では燈籠は木のうしろにいても、手洗いは上手かみてに立たなければならなかった。つくばいは人の手にふれるものだけに、たとえ隅の方にあっても品格は上手に位するものである。瑞雲院の庭のつくばいは二方の踏石から辿ることになり、一枚の短冊石を踏んで行くのであるがその打ち方も厳格であった。兼六園の池のきわの手洗いは大石であるが、三抱えくらいの椎の大樹の根元にしっかりと置かれ、雄心を遣るに豪邁であった。わたくしはまだこれほどの大樹の根元に置かれた手洗いを見たことはない。
つくばいの品格は最も秀すぐれたものでなければならず、形は大きくも小さくもない、程よい見馴染みなじみの快いものでなければならぬ。何となく奇岩めいた姿つきで、高峯一端の清韻を帯び、そのうえ雲霧を掻き起こすような気もちのものを尊ぶことは実際である。聊斎志異の白雲石の口碑のように穴あり時に綿のような雲を吐かねばたらぬ。そして鉢(水を入れるところ。)の中は古鏡のように澄み古色自ら在る体のものでなければならない。蒼い底に水をたたえた一基のつくばいは、何か庭の中に人あって鏡を見ているような心もちを起させるようである。実際、一掬の清水はよく庭裏の誠をうつすからである。
手洗いにはわたくしの知っている限りでは、普通のつくばいの外に、しゃれた石臼のような伽藍形があり、それは円い石に円い水鉢がうがたれている。最もっとしゃれたのに唐船というのは、自然石の鍬のような反りを持った石の左よりに水鉢があって、むかしの唐船のへんぽんたるに似ていて風致あるものである。司馬温公われまつばというのは三方に峯のある石のまん中が水鉢になり居り、風雅であるが居処いどころをきらうものであるから、鳥渡ちょっと据えるところに難しいしろものである。円星宿は普通の胴円どうまる通しの手洗いであるが、石水壺は先でひろがり底すぼまりの置水鉢で、石材次第で栄えるものだが、わたくしは嫌いである。却って石水瓶の三方取手のある枕型の胴すぼまりを面白いと思っている。支那朝鮮によくある大壺取手づきに似ていて、石であるため陶器以上のおもしろさである。陶器と石とは孰どちらが面白いかと言えば、味の細かいことは到底陶器には及ばないが、一味通じた底寂しい風韻枯寂の気がながれ合い、ときに陶器に見味うことのできぬところに、わたくしの心を惹き何かを思うさま捜らしてくれるのである。そのほか方星宿の四角なのもあるが、取り立てて言うまでもない。富士形、ひょうたん形に至っては、われわれ雅人と称するともがらには要なき俗手洗いである。つくばいは飽迄自然石を穿ったもので水鉢の磨きも叮嚀に寂然たるものでなければ面白くない。赤日石林気というのも又つくばいの銘でなければならない。
筧手洗いというのは高みにある手洗鉢に筧の水をしたたらすのであるが、これは生きているようで風致湧くごときものがある。凡兆の「古寺の簀の子も青し冬がまへ」という句があるが、何となくこの句の趣のような山住み山家の気持を表わすもので、春おそい日の永いころに筧の滴る音を書屋で聴くのはこころ憎いものである。その滴る水の流れ口を次第に低めにして自然に敷砂利しきじゃりの間を縫うてゆく趣の深さは、わざと細流をしつらえるより幽寂新鮮味は数倍するであろう。
四方仏というのは角胴四面に仏をきざんだのであるが、清韻愛すべきものである。わたくしは所謂難波寺形という大樹の下に据える手洗いに、姫蔦の蔓を這わしたことがあったが、蔦が石面一杯に蒸しつき、葉と葉との間に一掬の水が閑のどかに澄んでいるのは、まことに天来の穏かさを保って、限りなく美しいものである。茶庭では手洗いの前に湯桶手燭を置き、茶席の会中立前の所作の一つになっているそうである。わたくしは茶の方は詳しくないが、其行きとどいた精神にはいつも敬服している。茶道はまた色道に通ずというわたくしの哲学は、古今の茶道大義でなければならぬと思うている。清浄の中にいて色道を思うの情は、林泉に踞して亦垂鉤の境に蹲むと一般であろう。水光日を浮べ出て転た佳人を想うの心を誰も咎めるものはいない。こんな色道は枯れ侘びてなお余燈に対むかうようで、わたくしは好きである。遠州好みの茶庭のように大樹一本、小樹四五本、踏石を分けた中庭括り、八ツ窓茶室というような感じである。そのように整うところに何かの色があった。さびももとを掘じくり出すと何かの色が出て、褪めていて懐しいものである。
「庭を造る人」改造社
つくばい
1927(昭和2)年
.
2015年3月6日(金)
日本の庭
野鳥も想いのままに操る男。
アカイケ ヒロオミ。

ド~モ~!

純日本的な美しさの最も高いものは庭である。庭にはその知恵をうずめ、教養を匿して上に土を置いて誰にもわからぬようにしている。遠州や夢窓国師なぞは庭の学者であった。そうでない名もない庭作りの市井人が刻苦して作ったような庭に、匿された教養がある。
庭をつくるような人は陶器とか織物とか絵画とか彫刻とかは勿論、料理や木地やお茶や香道のあらゆるつながりが、実にその抜路に待ちかまえていることに、注意せずにいられない。結局精神的にもそうだが、あらゆる人間の感覚するところの高さ、品の好さ、匂いの深さにまで達しる心の用意がいることになる。人物ができていなければ庭の中にはいってゆけない、すくなくとも庭を手玉にとり、掌中に円めてみるような余裕が生じるまでは、人間として学ぶべきもののすべてを学んだ後でなければならぬような気がする。鉄のような精神的な健康もいるし、一茎の花にも心惹かれる柔かい詩人のたゆたいが要り、十人で引く石も指一本で動かす最後の仕上げにも、徹底的な勝利をも目ざしてその仕事につかねばならぬ。はいり込んで行けば生やさしいことは一つとして存在していない。この世界では、もうよかろうという言葉や、いい加減にしておこうということは、忌み嫌われる。進んだら退くことを知らぬ。庭作りの最後は財を滅ぼし市井の陋居に閉息するものが多い。
庭を見るということもその日の時間がたいせつであって、朝早く見て美しい庭もあろうし、午後の斜陽の射すころに栄える庭もあろうから、その庭の主人にいつごろがいいかということを打合せする必要がある。いきなり訪ねて庭を見せてくれということは無躾であって、読書している机のそばにいきなり訪ねて坐り込むようなものである。たいていの庭は午前なら十時ごろまでは日の射し方もななめにはしっているから、直射する午後一時から三時ごろを避ければ、夕方はどういう庭でも美しいという理由で、この二つの時間に庭を見ることで間違いはなく、無礼でないかも知れない。
夕方も大して暗くならない日没前一時間くらいなら、春夏秋冬を通じてまず夕暮の庭を見ることで、時間的に効果が多い。
その日没後すっかり暗くなるまでの庭を見、庭が夜の中に沈み込むのを見おさめることは、庭というものの精神を見てやるようなものである。しかしそれはその庭の主人がいつも見ているだけで、他人が見られない奥の深いところかもわからぬ。庭が夜の中に、襟を正して身づくろいしながら褥にはいるときは、その庭にあるものが一さいに融けあう美しい瞬間である。花も石も、木の幹も、みなそれぞれに見る人の心につながって来る。見る人に物思いがあり人のことを考えているなら花も、木、石も物思いの美しさを加え、殖やしてくれる。建築、造園、教養、叡智、学問、そんなものに思いをひそめている人がいたらその人は庭をみながら柔かく教養、叡智の捌け口を、手つだってくれることに気づく。滝田樗蔭氏は脇息にもたれ庭を見ながら雑誌に書いて貰う小説家や評論家を頭でえらんでいたそうであるが、滝田氏でなくとも建築家や事業を目ざす人びとが、その仕事を庭を見ながら組立てることもあるだろう。戦国時代の主将が明日の戦いに思いをひそめるためには、どれだけ庭の静かさが必要だったかわからない。
私は最近庭には木も石もいらないような気がし出した。垣根だけあればいい、垣根だけを見て、あとは土、あるいは飛石を見るか、苔を見るようにして木というものはできるだけすくなくまた石もできるだけ少なくしたいと考えるようになった。何故かといえば、庭で最初に眼につくは垣根であり、垣根は表からも裏からも座敷からも見えるからである。垣がいい垣ならそれだけ見ておればいい、小さい市井の庭ならなお垣だけ見られるようにしたいと考えている。竜安寺石庭の築地の塀があれらの虎の子渡しの石を抱いているのも、築地の塀が利かなかったら、石庭の輪郭と緊張が失われるように思える。市井の庭なら生垣にさまざまな四季の花時を見込んで、生垣仕立にすれば垣根だけで結構見られるのである。小さい庭に雑然と木を植え込んだ庭ほど緊張を失った生活を髣髴せしめるものはない、庭は日本の身だしなみであり、あそこにこそ、小さく貧しい庭であっても、日本の肌身がある。庭をつくるということは贅沢ではなく、生きた父とか母とかの歴史が、すぐ茶の間から見えるという、そんな親しさを身近に感じるとすれば、石一つ鳳仙花一本でも、その家の歴史を物語ってくれるものである。
すこし凝った庭なら築地の塀だけを見ていてもいい、瓦と土の塀を見ていれば、雑庭風な妄念を去ることができる。しかしここまで行くには、人は死に近づいていることが意味される。人はその生涯において派手な庭をつくり、そしてやがて瓦と土とを終日見ていて、もはや石や灯籠も、花も見なくなったといえば、やっと一人前の庭つくりになったといえよう。庭も何も持っていない人で、いつも庭を頭でつくっているような人がいたら、その人は最後に垣根と土とを見ていて十分に満足するかも知れぬ。天下の名園を見つくした人にはもはや何もいらないはずであった。
私は旅行中ある山中の小径で、稚木にどん栗が五六粒実っている枝を見てどん栗というものの実っている枝を美しいと思い、その生長を楽しんで東京にかえる日にその枝を持ってかえろうと、散歩のみぎり毎朝眺めて通っていた。どん栗は青く、何の役にも立たないくせに日を趁うてふとり、愛情をささやくごとく枝の間にふくれて行った。
ある朝、もうそろそろ剪ってもどろうと、鋏を用意して行って見ると子供のいたずららしく、どん栗は■り取られて一粒もあとを止めなかった。私は枝を見間違えたかと思ってさがして見たが、やはり子供が■り取って行った枝であった。茫然として人なき山中にくやしく私は唇を噛んだのである。
(一九四三年「日本の庭」)
アカイケ ヒロオミ。

ド~モ~!

「日本の庭」
室生犀星
純日本的な美しさの最も高いものは庭である。庭にはその知恵をうずめ、教養を匿して上に土を置いて誰にもわからぬようにしている。遠州や夢窓国師なぞは庭の学者であった。そうでない名もない庭作りの市井人が刻苦して作ったような庭に、匿された教養がある。
庭をつくるような人は陶器とか織物とか絵画とか彫刻とかは勿論、料理や木地やお茶や香道のあらゆるつながりが、実にその抜路に待ちかまえていることに、注意せずにいられない。結局精神的にもそうだが、あらゆる人間の感覚するところの高さ、品の好さ、匂いの深さにまで達しる心の用意がいることになる。人物ができていなければ庭の中にはいってゆけない、すくなくとも庭を手玉にとり、掌中に円めてみるような余裕が生じるまでは、人間として学ぶべきもののすべてを学んだ後でなければならぬような気がする。鉄のような精神的な健康もいるし、一茎の花にも心惹かれる柔かい詩人のたゆたいが要り、十人で引く石も指一本で動かす最後の仕上げにも、徹底的な勝利をも目ざしてその仕事につかねばならぬ。はいり込んで行けば生やさしいことは一つとして存在していない。この世界では、もうよかろうという言葉や、いい加減にしておこうということは、忌み嫌われる。進んだら退くことを知らぬ。庭作りの最後は財を滅ぼし市井の陋居に閉息するものが多い。
庭を見るということもその日の時間がたいせつであって、朝早く見て美しい庭もあろうし、午後の斜陽の射すころに栄える庭もあろうから、その庭の主人にいつごろがいいかということを打合せする必要がある。いきなり訪ねて庭を見せてくれということは無躾であって、読書している机のそばにいきなり訪ねて坐り込むようなものである。たいていの庭は午前なら十時ごろまでは日の射し方もななめにはしっているから、直射する午後一時から三時ごろを避ければ、夕方はどういう庭でも美しいという理由で、この二つの時間に庭を見ることで間違いはなく、無礼でないかも知れない。
夕方も大して暗くならない日没前一時間くらいなら、春夏秋冬を通じてまず夕暮の庭を見ることで、時間的に効果が多い。
その日没後すっかり暗くなるまでの庭を見、庭が夜の中に沈み込むのを見おさめることは、庭というものの精神を見てやるようなものである。しかしそれはその庭の主人がいつも見ているだけで、他人が見られない奥の深いところかもわからぬ。庭が夜の中に、襟を正して身づくろいしながら褥にはいるときは、その庭にあるものが一さいに融けあう美しい瞬間である。花も石も、木の幹も、みなそれぞれに見る人の心につながって来る。見る人に物思いがあり人のことを考えているなら花も、木、石も物思いの美しさを加え、殖やしてくれる。建築、造園、教養、叡智、学問、そんなものに思いをひそめている人がいたらその人は庭をみながら柔かく教養、叡智の捌け口を、手つだってくれることに気づく。滝田樗蔭氏は脇息にもたれ庭を見ながら雑誌に書いて貰う小説家や評論家を頭でえらんでいたそうであるが、滝田氏でなくとも建築家や事業を目ざす人びとが、その仕事を庭を見ながら組立てることもあるだろう。戦国時代の主将が明日の戦いに思いをひそめるためには、どれだけ庭の静かさが必要だったかわからない。
私は最近庭には木も石もいらないような気がし出した。垣根だけあればいい、垣根だけを見て、あとは土、あるいは飛石を見るか、苔を見るようにして木というものはできるだけすくなくまた石もできるだけ少なくしたいと考えるようになった。何故かといえば、庭で最初に眼につくは垣根であり、垣根は表からも裏からも座敷からも見えるからである。垣がいい垣ならそれだけ見ておればいい、小さい市井の庭ならなお垣だけ見られるようにしたいと考えている。竜安寺石庭の築地の塀があれらの虎の子渡しの石を抱いているのも、築地の塀が利かなかったら、石庭の輪郭と緊張が失われるように思える。市井の庭なら生垣にさまざまな四季の花時を見込んで、生垣仕立にすれば垣根だけで結構見られるのである。小さい庭に雑然と木を植え込んだ庭ほど緊張を失った生活を髣髴せしめるものはない、庭は日本の身だしなみであり、あそこにこそ、小さく貧しい庭であっても、日本の肌身がある。庭をつくるということは贅沢ではなく、生きた父とか母とかの歴史が、すぐ茶の間から見えるという、そんな親しさを身近に感じるとすれば、石一つ鳳仙花一本でも、その家の歴史を物語ってくれるものである。
すこし凝った庭なら築地の塀だけを見ていてもいい、瓦と土の塀を見ていれば、雑庭風な妄念を去ることができる。しかしここまで行くには、人は死に近づいていることが意味される。人はその生涯において派手な庭をつくり、そしてやがて瓦と土とを終日見ていて、もはや石や灯籠も、花も見なくなったといえば、やっと一人前の庭つくりになったといえよう。庭も何も持っていない人で、いつも庭を頭でつくっているような人がいたら、その人は最後に垣根と土とを見ていて十分に満足するかも知れぬ。天下の名園を見つくした人にはもはや何もいらないはずであった。
私は旅行中ある山中の小径で、稚木にどん栗が五六粒実っている枝を見てどん栗というものの実っている枝を美しいと思い、その生長を楽しんで東京にかえる日にその枝を持ってかえろうと、散歩のみぎり毎朝眺めて通っていた。どん栗は青く、何の役にも立たないくせに日を趁うてふとり、愛情をささやくごとく枝の間にふくれて行った。
ある朝、もうそろそろ剪ってもどろうと、鋏を用意して行って見ると子供のいたずららしく、どん栗は■り取られて一粒もあとを止めなかった。私は枝を見間違えたかと思ってさがして見たが、やはり子供が■り取って行った枝であった。茫然として人なき山中にくやしく私は唇を噛んだのである。
(一九四三年「日本の庭」)
2015年3月4日(水)
冬の庭
朝は
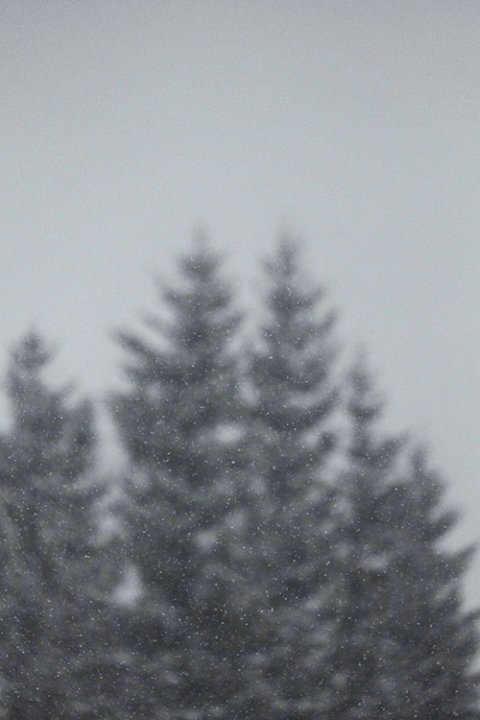
夕は

ご苦労様でした。
冬になると庭を眺める時がすくない。霜で荒れた土の上に箒をあてるといふわけにゆかないから、秋晩くに手入れを充分にして置かなければならない。この手入れさへ怠らなかつたら冬ぢゆうそのままにして置いてもよい。木の葉なぞも綺麗に掃き取つておけば、乱れるといふことはない。冬の庭の味ひの深いのは何といつても霜で荒れた土がむくみ出し、それが下ほど凍えて、上の方が灰のやうに乾いてゐる工合である。苔は苔のままむくみ上つてゐるところに、何とも言へぬ深い寂しみが蔵しまはれてゐて、踏んで見るとざつくりと土が沈む。乾いた灰ばんだ何処か蒼みのある土が耐らなく寂しい。掘り出しものの朝鮮の焼きもののやうな色と粉とから成り立つてゐるからである。
冬は庭木の根元を見ると、静かな気もちを感じさせる。灰ばんだ土へしつかりと埋め込まれて森乎しんとしながら、死んでゐるやうな穏かさをもつてゐるからである。庭を愛するひとびとよ、枝や葉を見ないで根元が土から三四寸離れたところを見たまへ。さういふ庭木の見かたもあることを心づいたら、わたくしの言ふことはないのである。
冬は四季を通じての庭のはらわたを見せるときである、庭の持主の心づかひが此の季節にすつかり表はれ、春夏秋の手入れや心配りの程が解るやうである。春夏秋の怠りもまた冬になると露あらわれるのである。池水がよごれて居れば氷が美しく見えない。木の掃除が行きとどいてゐなければ枯葉を乱すおそれがある。
何と言つても冬の庭は厳格と品とをもたなければならぬ。どれだけ厳格であつてもよい、むしろ厳格すぎて優しいところができれば、冬の庭としての全幅を含んでゐるやうである。冬の庭は障子硝子ガラスから一と目眺めたきり、それ以上眺めることがすくないものであるから、その瞬間に何かが視覚を打たなければならない。冬は寒いから庭のありさまも温かくしなければならぬといふのは俗説である。どこまでも深く鋭い方がよい。徒らな松の吊縄、藁のかげ法師、植木の巻藁まきわらなどはよくよく考へてから、その位置を作らなければならぬ。烏瓜の実の朱い色が凍み亘りその色が黒ずんでゆく、しまひに吊柿のやうな色になり干乾ひからびて種が鳴るやうになる。そこで初めて烏瓜の美しさが感じられるやうに、冬の庭も四季の終りに豁然として美事な眺めに就かなければならぬのである。
雪は冬の庭に永く眠つてゐるほど寂寞である。雪がきたらそのままによごさずに置くのである。雪に触つたところが一と処でもあれば、その睡り深い姿を掻き起す。寂寞が乱れてはならない。消える時もひとりで斑に美しく消えるにまかせるやうにする。手洗ひや、つくばひに張る氷も雪とともに厳格以上の厳格さをもつてゐる。冬の庭の要かなめを鏡のやうに磨き立てるものでなければならぬ。
冬の庭木としては別に特別なものはないが、梅擬うめもどきの実の朱いのが冬深く風荒んでくるころに、ぼろぼろ零こぼれるのはいいものである。南天の騒々しさにくらべると仲々澄んだ感じである。これは零れ落ちるときが最もよい。下草でも茎の強いもので実や穂になつたものは、そのまま冬も刈らずに置くと却つて風雅なものである。石蕗つわぶきの花も枯れたまま置くと侘びた姿で春まで残つてゐる。砥草とくさなどは北風にさらされる方の茎の色が茜色に焼け、さかんな水気を吸ひ上げ尖端さきを蕭條と枯らしてゐるなど冬の色である。砥草はまとめて植ゑるよりも斑に七八本づつ乱して置く方がいいことを冬に入つてから知つた。
枸杞くこの実の斑に残つたのは、その朱い実を見つめてゐるだけでも、悲しくなる或る種類の愛情をもつてゐるものである。八ツ手の花は品はないが朝霜の中では清冽な一脈の気焔を上げてゐる。黒ずんでくるころは仲々美しい。
山茶花は白いほど品がよく淡紅はよくない。蕾のころか零れ散るころかがわたくしの心に叶うてゐる。枇杷や茶の花は枯淡以上のもので、枇杷になると花ではなく、古い陶画の一部を剥ぎ取つたやうに思へる。茶の花の方がいくらか枇杷よりか優しくあでやかだ。珊さんたる蕾の姿は霰や餅米のやうに小粒で美しい、どこか庭のすみの方に二三株、目立たぬほどに植ゑて置く心がけを侑すすめるくらゐで、ぢみな花である。しかしその実に至つては天来の寂しみをもつて、割れて口を開けその根元に種をこぼす、母のこころをもつてゐる懐しいものである。わたくしはよく椿の実を枝にたづねたものであるが、茶の花は根元の土の上を捜たずねる方が、早く種が見つかりさうである。全く茶の実は枝にはなく土の上にこぼれてゐるからである。
わたくしはこのごろ松竹梅といふ三点樹を昔の人がさう言ひならしてゐる言葉に感心してゐる。松竹梅といふと古い言草であるが、松といひ竹といひ又梅といふは樹の中の三兄妹であつて、三樹交契のいみじさ美しさは喞々としてわたくしの心に何かを囁いてくるのだ。木の世界の王さまでなければならぬ。実際この三樹交契を以つて庭を作るとしたら最早何ものも要らない。昔から此の木々をもつてめでたいものの標本とした。その故深い意味が意味ばかりでなく、心までさう感じさせて来たのは恥かしながらわたくしに取つては最近のことである。あまりに目に触れすぎたため此の三樹交契が日本人の性分をこまかに織り出してゐたことさへ忘れてゐた程であつた。芭蕉の俳風も眼を閉ぢて思へばこれらの三樹交契の幽韻の内にもあるやうである。もつと進んで考へると此の交契の奥深くに吾らの祖先が一幅を圧して坐つてゐたことも思はれるのである。
松のその風籟の音に秀でてゐるは言ふまでもないが、一群の清韻は遥に天に向つて何ものかを奏でてゐるやうである。葉も枝もよいがその音を取らねばならぬ。西行、芭蕉の道であらう。竹はすぐな心を表はしてゐるやうで陳腐であるが左う考へる方が、無理がないやうである。かれは寂しいが喜んでゐるやうな木である。絶えず愉快な表情の中に、流れるやうな寂しさをもつてゐる。そして雨とか雪とかになほ一層その奥の手をみがき出してゐるやうである。
梅に至つては匂ひであらう。
庭は隅の方から作つてゆく。一つの隅を作り終へたら、又次ぎの隈の一部から畳んでゆくのである。そして三方或ひは四方から作りあげてゆくうちに、庭の中心がひとりでに出来あがるのだ。庭のまん中から作つて行つたら滅多めつたにかたがつくことがない。魚を料理つくるにまん中から庖丁を入れることは、料理ることを知らない人のすることである。腹や頭から庖丁を入れねばならぬ。それと同じやうに隅から作りあげ、ひとりでに中心を残して行つたら、そこで中心をぎゆつと縮めるやうな心で、最後に帳〆をするのであるが、この一点の仕上げの行き方で、庭を活かすとも殺すともできるのである。
.
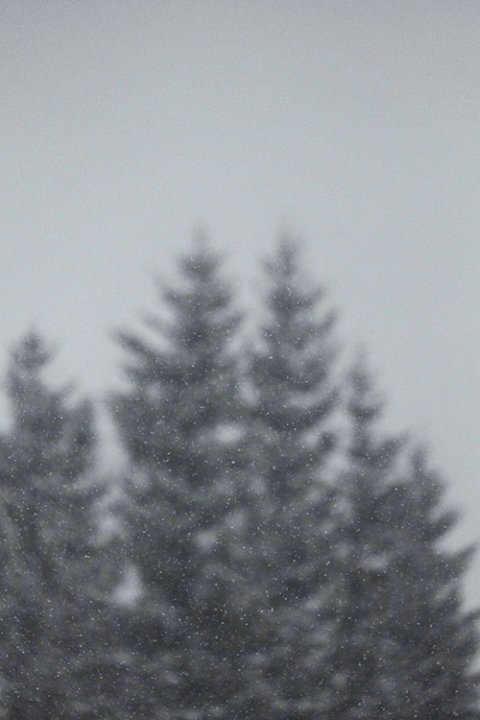
夕は

ご苦労様でした。
「冬の庭」
室生犀星
冬になると庭を眺める時がすくない。霜で荒れた土の上に箒をあてるといふわけにゆかないから、秋晩くに手入れを充分にして置かなければならない。この手入れさへ怠らなかつたら冬ぢゆうそのままにして置いてもよい。木の葉なぞも綺麗に掃き取つておけば、乱れるといふことはない。冬の庭の味ひの深いのは何といつても霜で荒れた土がむくみ出し、それが下ほど凍えて、上の方が灰のやうに乾いてゐる工合である。苔は苔のままむくみ上つてゐるところに、何とも言へぬ深い寂しみが蔵しまはれてゐて、踏んで見るとざつくりと土が沈む。乾いた灰ばんだ何処か蒼みのある土が耐らなく寂しい。掘り出しものの朝鮮の焼きもののやうな色と粉とから成り立つてゐるからである。
冬は庭木の根元を見ると、静かな気もちを感じさせる。灰ばんだ土へしつかりと埋め込まれて森乎しんとしながら、死んでゐるやうな穏かさをもつてゐるからである。庭を愛するひとびとよ、枝や葉を見ないで根元が土から三四寸離れたところを見たまへ。さういふ庭木の見かたもあることを心づいたら、わたくしの言ふことはないのである。
冬は四季を通じての庭のはらわたを見せるときである、庭の持主の心づかひが此の季節にすつかり表はれ、春夏秋の手入れや心配りの程が解るやうである。春夏秋の怠りもまた冬になると露あらわれるのである。池水がよごれて居れば氷が美しく見えない。木の掃除が行きとどいてゐなければ枯葉を乱すおそれがある。
何と言つても冬の庭は厳格と品とをもたなければならぬ。どれだけ厳格であつてもよい、むしろ厳格すぎて優しいところができれば、冬の庭としての全幅を含んでゐるやうである。冬の庭は障子硝子ガラスから一と目眺めたきり、それ以上眺めることがすくないものであるから、その瞬間に何かが視覚を打たなければならない。冬は寒いから庭のありさまも温かくしなければならぬといふのは俗説である。どこまでも深く鋭い方がよい。徒らな松の吊縄、藁のかげ法師、植木の巻藁まきわらなどはよくよく考へてから、その位置を作らなければならぬ。烏瓜の実の朱い色が凍み亘りその色が黒ずんでゆく、しまひに吊柿のやうな色になり干乾ひからびて種が鳴るやうになる。そこで初めて烏瓜の美しさが感じられるやうに、冬の庭も四季の終りに豁然として美事な眺めに就かなければならぬのである。
雪は冬の庭に永く眠つてゐるほど寂寞である。雪がきたらそのままによごさずに置くのである。雪に触つたところが一と処でもあれば、その睡り深い姿を掻き起す。寂寞が乱れてはならない。消える時もひとりで斑に美しく消えるにまかせるやうにする。手洗ひや、つくばひに張る氷も雪とともに厳格以上の厳格さをもつてゐる。冬の庭の要かなめを鏡のやうに磨き立てるものでなければならぬ。
冬の庭木としては別に特別なものはないが、梅擬うめもどきの実の朱いのが冬深く風荒んでくるころに、ぼろぼろ零こぼれるのはいいものである。南天の騒々しさにくらべると仲々澄んだ感じである。これは零れ落ちるときが最もよい。下草でも茎の強いもので実や穂になつたものは、そのまま冬も刈らずに置くと却つて風雅なものである。石蕗つわぶきの花も枯れたまま置くと侘びた姿で春まで残つてゐる。砥草とくさなどは北風にさらされる方の茎の色が茜色に焼け、さかんな水気を吸ひ上げ尖端さきを蕭條と枯らしてゐるなど冬の色である。砥草はまとめて植ゑるよりも斑に七八本づつ乱して置く方がいいことを冬に入つてから知つた。
枸杞くこの実の斑に残つたのは、その朱い実を見つめてゐるだけでも、悲しくなる或る種類の愛情をもつてゐるものである。八ツ手の花は品はないが朝霜の中では清冽な一脈の気焔を上げてゐる。黒ずんでくるころは仲々美しい。
山茶花は白いほど品がよく淡紅はよくない。蕾のころか零れ散るころかがわたくしの心に叶うてゐる。枇杷や茶の花は枯淡以上のもので、枇杷になると花ではなく、古い陶画の一部を剥ぎ取つたやうに思へる。茶の花の方がいくらか枇杷よりか優しくあでやかだ。珊さんたる蕾の姿は霰や餅米のやうに小粒で美しい、どこか庭のすみの方に二三株、目立たぬほどに植ゑて置く心がけを侑すすめるくらゐで、ぢみな花である。しかしその実に至つては天来の寂しみをもつて、割れて口を開けその根元に種をこぼす、母のこころをもつてゐる懐しいものである。わたくしはよく椿の実を枝にたづねたものであるが、茶の花は根元の土の上を捜たずねる方が、早く種が見つかりさうである。全く茶の実は枝にはなく土の上にこぼれてゐるからである。
わたくしはこのごろ松竹梅といふ三点樹を昔の人がさう言ひならしてゐる言葉に感心してゐる。松竹梅といふと古い言草であるが、松といひ竹といひ又梅といふは樹の中の三兄妹であつて、三樹交契のいみじさ美しさは喞々としてわたくしの心に何かを囁いてくるのだ。木の世界の王さまでなければならぬ。実際この三樹交契を以つて庭を作るとしたら最早何ものも要らない。昔から此の木々をもつてめでたいものの標本とした。その故深い意味が意味ばかりでなく、心までさう感じさせて来たのは恥かしながらわたくしに取つては最近のことである。あまりに目に触れすぎたため此の三樹交契が日本人の性分をこまかに織り出してゐたことさへ忘れてゐた程であつた。芭蕉の俳風も眼を閉ぢて思へばこれらの三樹交契の幽韻の内にもあるやうである。もつと進んで考へると此の交契の奥深くに吾らの祖先が一幅を圧して坐つてゐたことも思はれるのである。
松のその風籟の音に秀でてゐるは言ふまでもないが、一群の清韻は遥に天に向つて何ものかを奏でてゐるやうである。葉も枝もよいがその音を取らねばならぬ。西行、芭蕉の道であらう。竹はすぐな心を表はしてゐるやうで陳腐であるが左う考へる方が、無理がないやうである。かれは寂しいが喜んでゐるやうな木である。絶えず愉快な表情の中に、流れるやうな寂しさをもつてゐる。そして雨とか雪とかになほ一層その奥の手をみがき出してゐるやうである。
梅に至つては匂ひであらう。
庭は隅の方から作つてゆく。一つの隅を作り終へたら、又次ぎの隈の一部から畳んでゆくのである。そして三方或ひは四方から作りあげてゆくうちに、庭の中心がひとりでに出来あがるのだ。庭のまん中から作つて行つたら滅多めつたにかたがつくことがない。魚を料理つくるにまん中から庖丁を入れることは、料理ることを知らない人のすることである。腹や頭から庖丁を入れねばならぬ。それと同じやうに隅から作りあげ、ひとりでに中心を残して行つたら、そこで中心をぎゆつと縮めるやうな心で、最後に帳〆をするのであるが、この一点の仕上げの行き方で、庭を活かすとも殺すともできるのである。
.
2015年3月2日(月)
雪に
2015年2月25日(水)
なぜ小鳥はなくか









「星野君のヒント」
田村 隆一
「なぜ小鳥はなくか」
プレス・クラブのバーで
星野君がぼくにあるアメリカ人の詩を紹介した
「なぜ人間は歩くのか これが次の行だ」
われわれはビールを飲み
チーズバーグをたべた
コーナーのテーブルでは
初老のイギリス人がパイプに火をつけ
夫人は神と悪魔の小説に夢中になっていた
九月も二十日すぎると
この信仰のない時代の夜もすっかり秋のものだ
ほそいアスファルトの路をわれわれは黙って歩き
東京駅でわかれた
「なぜ小鳥はなくか」
ふかい闇のなかでぼくは夢からさめた
非常に高いところから落ちてくるものに
感動したのだ
そしてまた夢のなかへ「次の行」へ
ぼくは入っていった

.









