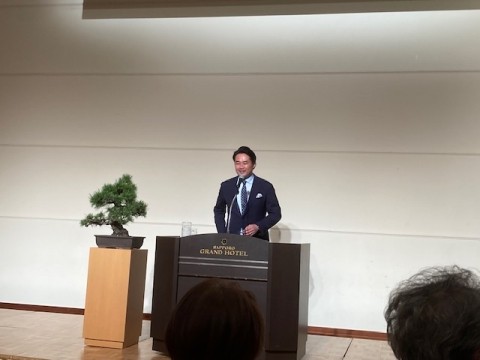2024年1月28日(日)
地域を活性化する~杉村太蔵先生の話を聞いてきました
2024年1月15日(月)
戸籍のお話
2024年1月13日(土)
ナンバープレートの後返納制度について
行政書士業務×164
車の名義変更や住所変更のためにナンバープレートが変わる場合は、元のナンバープレートを返納しないといけません。
ナンバープレートを外してしまうとその日は車を使えませんから、平日に車を使えないと困る、という方は大変です。
そんな方向けに、便利なナンバープレート後返納制度 のご紹介です。
のご紹介です。
お仕事が終わった後や、お休みの日でも対応可能ですので、なかなか運輸支局に行けないという方は是非ご利用ください。
ナンバープレートを外してしまうとその日は車を使えませんから、平日に車を使えないと困る、という方は大変です。
そんな方向けに、便利なナンバープレート後返納制度
 のご紹介です。
のご紹介です。お仕事が終わった後や、お休みの日でも対応可能ですので、なかなか運輸支局に行けないという方は是非ご利用ください。
2024年1月8日(月)
十勝の車庫証明事情~管轄エリアや距離について
行政書士業務×164
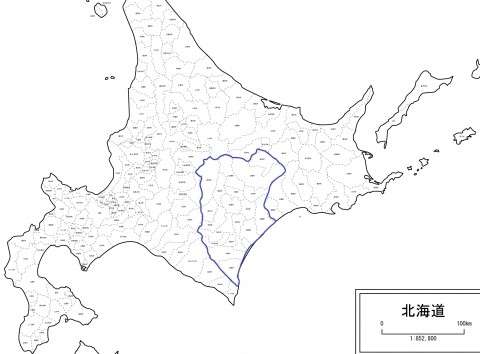
十勝は帯広署・新得署・池田署・本別署・広尾署の5つの管轄に分かれており、それぞれが別の市町村の車庫証明を管轄しています。
遠い地域だと100km以上離れていることもしばしばですが、どのエリアでも対応可能です。
書類作成はこちらで行いますので、使用者様と車両の情報と自認書/使用承諾書のみご用意ください。
十勝の車庫証明のお問い合わせはこちらをご覧ください。<
もちろん、自動車の登録、出張封印についても対応可能です。
出張封印は、夜間や休日しか在宅していない方でもご依頼いただけます。
遠い地域だと100km以上離れていることもしばしばですが、どのエリアでも対応可能です。
書類作成はこちらで行いますので、使用者様と車両の情報と自認書/使用承諾書のみご用意ください。
十勝の車庫証明のお問い合わせはこちらをご覧ください。<

もちろん、自動車の登録、出張封印についても対応可能です。
出張封印は、夜間や休日しか在宅していない方でもご依頼いただけます。
2023年9月28日(木)
HP移転のお知らせ
| << | >> |