2024年2月2日(金)
幸楽苑のラーメン 中国の友人が高評価
a 他トピック Others×235

中国の友人と夕食に行った。何が食べたい?と聞いたら「日本の代表的ラーメンを食べたい」とのこと。これは下手をすると日本のラーメンの評判を落とすことになるので責任重大だ。淡白なもの?それとも油が沢山?辛いの?と聞いたら「オイリーでも構わない。日本的なもの」と言われ困ってしまった。最近の中国では豚骨系の一風堂が評判になりつつあるが「オイリーでも構わないと言うのは豚骨系ではないな」と思い 意を決して近くの幸楽苑に入った。
彼女が選択したのは「チャーシューラーメンと焼き餃子の定食」だった。結果は「おいしい・おいしい」とほぼ完食したので驚いた。
 自分はおとなしく「レバニラ定食」にしたが「何それ?おいしいの?」と聞かれる始末。あまり興味がなさそうだ。そうかもしれない。
自分はおとなしく「レバニラ定食」にしたが「何それ?おいしいの?」と聞かれる始末。あまり興味がなさそうだ。そうかもしれない。
中国の人はおいしい日常食を探すのが得意だ。その意味で幸楽苑のスープと麺を評価したのだろう。「中国のラーメンは基本的には牛で 豚は使わない」「この日本のラーメンはおいしい」という評価だった。
また中国では餃子はもっちりとした水餃子がほとんどで 焼き餃子はまずないので 焼き餃子のハネを面白がっていた。
幸楽苑のラーメンを絶品だという日本人は必ずしも多くは無いと思うが(個人的感想) 中国人の舌には合格点のようだ。安心した。
訂正とお詫び: 2か月前の写真だったため 最初の稿で山岡家と誤記してしまいました。お詫びの上 幸楽苑に訂正させていただきます。
彼女が選択したのは「チャーシューラーメンと焼き餃子の定食」だった。結果は「おいしい・おいしい」とほぼ完食したので驚いた。

中国の人はおいしい日常食を探すのが得意だ。その意味で幸楽苑のスープと麺を評価したのだろう。「中国のラーメンは基本的には牛で 豚は使わない」「この日本のラーメンはおいしい」という評価だった。
また中国では餃子はもっちりとした水餃子がほとんどで 焼き餃子はまずないので 焼き餃子のハネを面白がっていた。
幸楽苑のラーメンを絶品だという日本人は必ずしも多くは無いと思うが(個人的感想) 中国人の舌には合格点のようだ。安心した。
訂正とお詫び: 2か月前の写真だったため 最初の稿で山岡家と誤記してしまいました。お詫びの上 幸楽苑に訂正させていただきます。
2024年2月1日(木)
札幌雪祭りは開幕直前 雪は足りたようだ
c 札幌・道央圏Sapporo×253

札幌医大近くに用事があり 帰りがけに大通公園を歩いてみた。今年の雪まつり期間は2/4~11なので 開幕直前に雪像の出来具合を見ようと思ったのだが もちろん運動不足解消でもある。一番西側の市民雪像のと製作はだいぶ進んでいた。
 ミュンヘン広場の11丁目あたりは雪や重機の置き場で雪像はない。
ミュンヘン広場の11丁目あたりは雪や重機の置き場で雪像はない。
 この日は寒くて強風。急に吹雪いて一瞬で回りが暗くなった。
この日は寒くて強風。急に吹雪いて一瞬で回りが暗くなった。
 10丁目の市民雪像群は一所懸命で製作中。赤い顔で寒そうだ。
10丁目の市民雪像群は一所懸命で製作中。赤い顔で寒そうだ。
 7丁目位から自衛隊さんの車両があり ステージ付きの雪像が製作中。ただし昔の大雪像よりはだいぶ小さくて中雪像の感じ。
7丁目位から自衛隊さんの車両があり ステージ付きの雪像が製作中。ただし昔の大雪像よりはだいぶ小さくて中雪像の感じ。
 ステージの雪製バックスクリーンにプロジェクションの試験をしてるようだ。
ステージの雪製バックスクリーンにプロジェクションの試験をしてるようだ。
 雪まつり本番では会場通路は一方通行だが 現在は通行止めなので 歩行者は公園横の歩道を使っている。旅行カバンを転がしている人もチラホラ。雪まつりの事前見物のようだ。
雪まつり本番では会場通路は一方通行だが 現在は通行止めなので 歩行者は公園横の歩道を使っている。旅行カバンを転がしている人もチラホラ。雪まつりの事前見物のようだ。
 これは比較的大きい雪像だが 通行止めなので全体が見えない。何か屯田兵のイメージがする。
これは比較的大きい雪像だが 通行止めなので全体が見えない。何か屯田兵のイメージがする。
 4丁目まで来ると駅前通りはLEDイルミネーションだった。歩行者はパラパラだ。
4丁目まで来ると駅前通りはLEDイルミネーションだった。歩行者はパラパラだ。
 地下に降りると地下街・大通駅あたりは人がいっぱい。雪像が完成していないし寒いので地上には誰も行かないわな。
地下に降りると地下街・大通駅あたりは人がいっぱい。雪像が完成していないし寒いので地上には誰も行かないわな。
ということで「開幕直前でも雪像は工事中」だったが 今年の雪は何とかなったようだ。









ということで「開幕直前でも雪像は工事中」だったが 今年の雪は何とかなったようだ。
2024年2月1日(木)
暖気の一月末 歩道の雪解け
c 札幌・道央圏Sapporo×253

札幌ではここ数日の昼間はプラス気温だ。最近は家にこもりきりで運動不足になってしまった。近所の用事は歩いていくことにしているが 歩道はガタガタで歩きづらい。
当然だが表通りは路面が出て濡れた状態。
 中通りから車が出てくる場所は このような水たまり。
中通りから車が出てくる場所は このような水たまり。
 一方 キレイに除雪機が入った歩道では真ん中がテカテカで みんなが端を通るのでかまぼこ状になる。
一方 キレイに除雪機が入った歩道では真ん中がテカテカで みんなが端を通るのでかまぼこ状になる。
 中途半端に除雪した日陰側の車庫前はテカテカ。いやだいやだ。
中途半端に除雪した日陰側の車庫前はテカテカ。いやだいやだ。
 これは春先のポットホールではなくて マンホールの上が解けた穴。段差は10センチ近くか。車高の低い車だとはまるだろう。
これは春先のポットホールではなくて マンホールの上が解けた穴。段差は10センチ近くか。車高の低い車だとはまるだろう。
 中通りを見渡すとテカテカ光っている。
中通りを見渡すとテカテカ光っている。
明日から天気が崩れて雪も降るらしい。この上に雪がかぶるととんでもないことになる。要注意だ。冬将軍はなかなか甘くない。
当然だが表通りは路面が出て濡れた状態。





明日から天気が崩れて雪も降るらしい。この上に雪がかぶるととんでもないことになる。要注意だ。冬将軍はなかなか甘くない。
2024年1月30日(火)
東京駅で豚丼のたれを売っていた!
a 他トピック Others×235

十勝ヒュッテのメンバーで東京在住のWさんから「東京駅地下街で十勝豚丼のたれを売っていた!」とLineがあった。「とても美味しい味付けだった」とのこと。
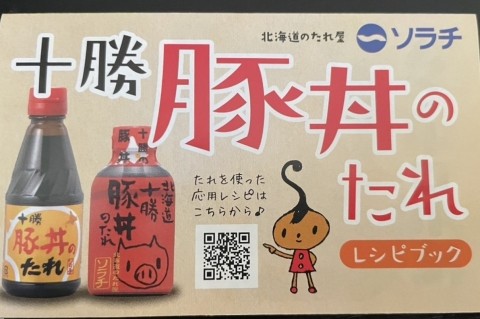 レシピブックを見ると「ソラチのたれ」のようだ。全国的展開には ある程度大きい会社のまとまった数のロッドが必要なのだろう。とにかく十勝豚丼が日本中の家庭に浸透していくことは大歓迎だ。次にはあのおいしい十勝の豚肉を期待したい。
レシピブックを見ると「ソラチのたれ」のようだ。全国的展開には ある程度大きい会社のまとまった数のロッドが必要なのだろう。とにかく十勝豚丼が日本中の家庭に浸透していくことは大歓迎だ。次にはあのおいしい十勝の豚肉を期待したい。
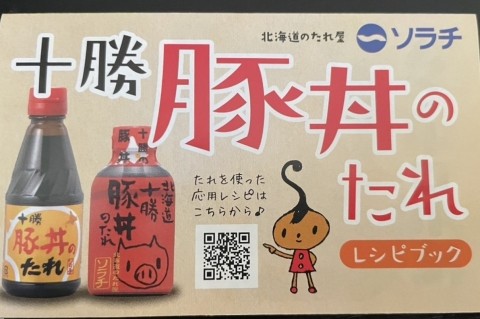
2024年1月29日(月)
軽四駆テリオスキッド 文句は沢山 がメリットも
愛車いろいろ×21

免許を取ってから40年超 いろいろな車に乗ってきた。クロカン系の四駆が好みで ジムニー・ランクル70/60・ビッグホーン レンタカーならエクスプローラにも乗った。直近のビッグホーンは2台を30万キロ近くまで乗り継いだが 故障が多発して2年前に売却(それでも売れた)。その後は十勝ヒュッテの建設も一段落して荷物も減ったので「軽でいいだろう」とパジェロミニに。これもAT不良で次を探し 昨年4月から「テリオスキッド」になった。一番の理由は「ダイハツは乗ったことがないから」だった。
 ポイントはタイヤ径が大きめで(175/80R16) 地上高が20センチ位はあること。また何と言っても安いのが有難い(最近のジムニーは腹が立つほど高い)。幸い 年式は古いが5万キロの程度のいいTKが見つかったので昨年4月にユーザー車検を通した。
ポイントはタイヤ径が大きめで(175/80R16) 地上高が20センチ位はあること。また何と言っても安いのが有難い(最近のジムニーは腹が立つほど高い)。幸い 年式は古いが5万キロの程度のいいTKが見つかったので昨年4月にユーザー車検を通した。
 乗り始めたら 実は不満だらけ。シートが悪い・距離メーターが見づらい・パワー不足(軽なので仕方ないが)などきりがない。でも燃費は評価出来て3000回転位を使っていれば16km/リッターはいく(市内だと10km/リッターを下回るが)。タイヤが軽くて脱着が楽なのと 地上高が十分で雪に強い(エアロは下腐れを誘発するので不要)。また 5ドアは使い勝手がいい。
乗り始めたら 実は不満だらけ。シートが悪い・距離メーターが見づらい・パワー不足(軽なので仕方ないが)などきりがない。でも燃費は評価出来て3000回転位を使っていれば16km/リッターはいく(市内だと10km/リッターを下回るが)。タイヤが軽くて脱着が楽なのと 地上高が十分で雪に強い(エアロは下腐れを誘発するので不要)。また 5ドアは使い勝手がいい。
 冬期になってわかったのだが この車はフルタイム四駆だが 悪路に備えて「センターデフロック」が付いていて(写真の四駆サイン) これは非常に具合がよくお勧めだ。ただしパートタイムのLモードがないので極低速で扱う時は要注意だ。
冬期になってわかったのだが この車はフルタイム四駆だが 悪路に備えて「センターデフロック」が付いていて(写真の四駆サイン) これは非常に具合がよくお勧めだ。ただしパートタイムのLモードがないので極低速で扱う時は要注意だ。
 またこのデフロックスイッチはハンドルの影にあるので 手探りでひどく面倒だ。
またこのデフロックスイッチはハンドルの影にあるので 手探りでひどく面倒だ。
TKは1998年から2012年まで生産された。最近になって意外に多く市中を走っているのに気が付いた。絶版車なので今更とやかく言っても仕方がないが 中古車を購入する方には参考になるかもしれない。




TKは1998年から2012年まで生産された。最近になって意外に多く市中を走っているのに気が付いた。絶版車なので今更とやかく言っても仕方がないが 中古車を購入する方には参考になるかもしれない。
